SDGsの目標2「飢餓をゼロに」とは?概要や取り組み事例などを解説
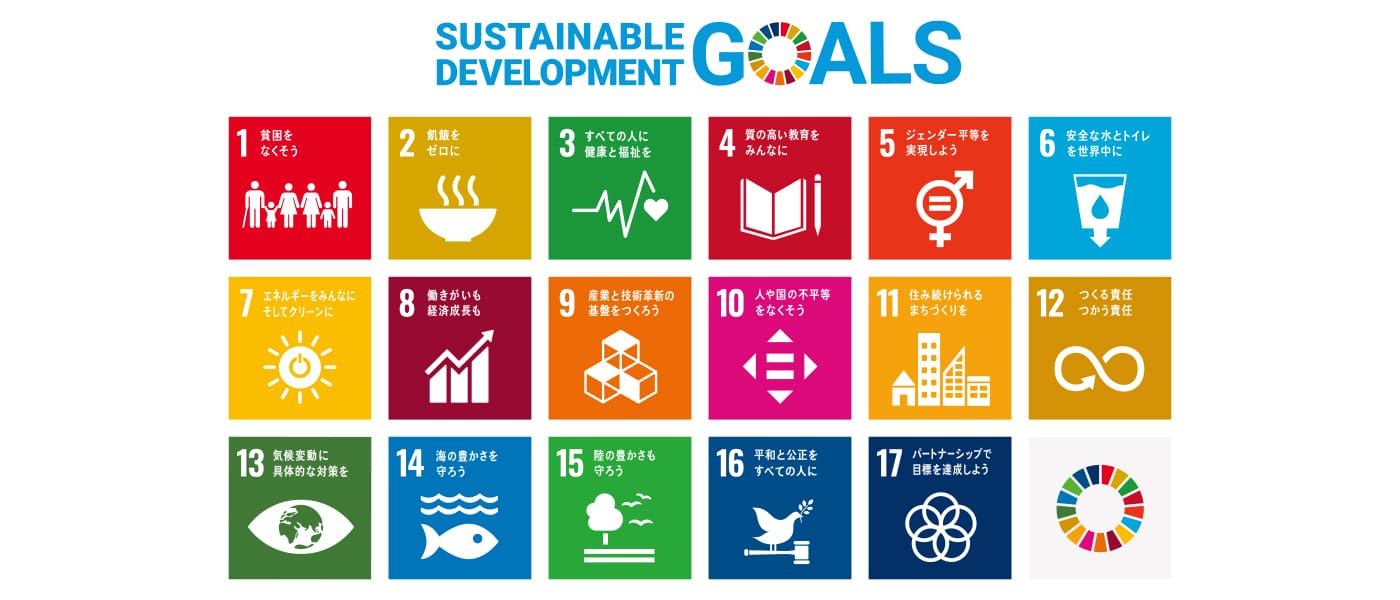
SDGs(エスディージーズ Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)とは、2001年に策定されたMDGs(ミレニアム開発目標)の後継のもので、2016年から2030年までの国際目標です。2015年9月に国連サミットで取り上げられました。
SDGsは2030年までに、持続可能でより良い世界の実現を目指します。17のゴールと169のターゲットから構成され、全人類が取り組むべき普遍的な目標です。
本記事では、目標2「飢餓をゼロに」についての概要や取り組み事例、今後の課題などを解説します。
この記事は下記の内容構成になります
・目標2「飢餓をゼロに」はどんな目標?
・目標2「飢餓をゼロに」ができた背景と問題解決に必要なこと
・飢餓をなくすための取り組み事例
≫キューピー株式会社の取り組み
≫JALグループの取り組み
≫株式会社フェアトレードコットンイニシアティブの取り組み
・企業や個人ができることや、今後の課題について
・目標2「飢餓をゼロに」についてのまとめ
目標2「飢餓をゼロに」はどんな目標?
国連開発計画によると、「2030年までにあらゆる形態の飢餓と栄養不良に終止符を打ち、子どもや社会的弱者を始めとするすべての人が、1年を通じて栄養のある食料を十分に得られるようにすることを狙いとしています。」とあります。
この目標達成のためには、農家の生活と能力を向上させたり、土地や技術、市場へ誰もがアクセスできる環境を与えたりして、持続可能な農業の指導をしなければなりません。また、国際協力のもと農業生産性を改善することも必要です。
目標2「飢餓をゼロに」ができた背景と問題解決に必要なこと

現在でも飢餓で苦しむ国や地域があります。特に子どもが飢餓になると、成長が遅れたり早くに命を落としたりするため、その国や地域の発展の遅れにもつながっています。この状況を改善するべく、目標2「飢餓をゼロに」が策定されました。
飢餓が起こりやすい「自然災害」や「紛争」が多発する地域を中心に、食料を確保する貯蔵庫や農業技術の向上が求められます。先進国が途上国にノウハウを伝えて、持続可能である農業の仕組みを構築することが必要です。
安定的で持続可能な農業が途上国に浸透すれば、そこで働く人たちの収入にもつながるため、好循環が生み出せます。
飢餓をなくすための取り組み事例
飢餓をなくすために企業が取り組んでいる事例を3つご紹介します。
キューピー株式会社の取り組み
「飢餓」とは必ずしも食糧不足だけでなく、低栄養の状態も含まれます。このことからキューピーは「高齢になっても元気で過ごせるように、健康寿命を延ばす」ことに貢献しています。具体的には、サラダ(野菜)と卵を中心としたさまざまな食の提案です。
また、食品メーカーとして食資源を有効活用するために卵の殻を100%リサイクルしたり、持続可能な農業支援をおこなったりしています。
JALグループの取り組み
JALグループが参画している取り組みに「TABLE FOR TWO 社員食堂プログラム」があります。これは開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消を目指した日本発の社会貢献プログラムです。
具体的には、対象メニュー1品につき20円がTABLE FOR TWO事務局に寄付されます。寄付金は開発途上国の子どもたちの学校給食事業にあてられ、20円が開発途上国での学校給食1食分に相当する金額だそうです。
株式会社フェアトレードコットンイニシアティブの取り組み
Unicefによると、インドでは学校に通っていない子ども(7歳〜14歳)の40が働いていると報告されています。
株式会社フェアトレードコットンイニシアティブは、オーガニックコットンの生産量が世界最大であるインドで、フェアトレードに取り組んでいます。綿花の購入から製品化までをすべて直接インドのビジネスパートナー企業とおこなうことで、適正な労働環境と賃金を守っているのです。
企業や個人ができることや、今後の課題について

実は日本でも相対的貧困層を中心に飢餓に苦しむ国民がいます。相対的貧困とは、貧困線(2018年は127万円)に満たない所得で生活すること。2018年の相対的貧困率は15.4で、国民の約6.5人に1人が年127万円未満の所得で生活していることになります。そのなかには飢餓で苦しむ人たちが一定数いると推測できるのです。
日本で飢餓に苦しむ人たちを企業や個人が直接助けることは難しいかもしれません。ただ、飢餓が広がる社会を防ぐためにできることはあります。
たとえば日本では、安全に食べられるのに流通に出せない食品を施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動をおこなったり、フードシェアリングサービスを展開したりする企業があります。このような活動が、食料を社会の隅々まで行き渡らせるセーフティネットとして機能すれば、飢餓で苦しむ人たちを救うチャンスも増えるでしょう。
飢餓を防ぐための行動は、個人では限界があります。各国政府、市民、そして民間企業が力を合わせて投資と技術革新を行う必要があります。
目標2「飢餓をゼロに」についてのまとめ
飢餓のない世界を実現するにはまだ長い道のりがあります。飢餓と栄養不良をなくすことは、全人類にとって大きな課題の1つです。
十分な食事をとれなかったり、質が悪かったりすると、人々の健康状態が悪化するだけでなく、教育や雇用などの発展を遅らせることにもなります。
私たちも普段から「自分にできること」を実践していきましょう。
前回の記事はコチラ≫【SDGs目標1.貧困をなくそう】

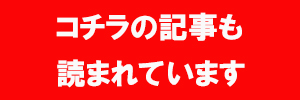
スクラップ関連記事
非鉄金属ってなに?
鉄・鉄屑ってなに?
スクラップってなに?
銅スクラップってなに?
真鍮スクラップってなに?
アルミニウムってなに?
ステンレスってなに?
電線スクラップってなに?
鉛スクラップってなに?
バッテリースクラップってなに?
コモンメタル
ベースメタル
金属買取業者の選び方
金属の売り方
リサイクルショップと金属買取業者の違い
リサイクルショップの開業の仕方
金属買取業者の開業の仕方
古物商について
金属屑業について
使用済み有害機器について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
環境・SDGs関係の記事を発信しています
ゼロカーボンアクションについて解説
リサイクル業者のゼロカーボンチャレンジ宣言
≫脱炭素戦略「カーボンゼロチャレンジ2050」策定
グリーンライフポイントの制度・概要や対象ジャンル
サステナブルな暮らしをするための具体的な方法
3R(スリーアール)
リサイクルとは?
≫金属リサイクルのデメリット
≫廃車のリサイクルと簡単な廃車手続き【税金の返金や還付】
リユースについて
≫アップサイクルとダウンサイクル
≫簡単なバイクの処分とリユース
リサイクル企業の視点から考えるSDGs
リデュースってなに?
0.SDGsってなに?
SDGs1.貧困をなくそう
≫SDGsの目標1の概要や取り組み事例などを解説
SDGs2.飢餓をゼロに
≫SDGsの目標2の概要や取り組み事例などを解説
≫10/30は食品ロス削減の日
SDGs3.すべての人に健康と福祉を
≫SDGsの目標3の概要や取り組み事例などを解説
SDGs4.質の高い教育をみんなに
≫SDGsの目標4の概要や取り組み事例などを解説
SDGs5.ジェンダー平等を実現しよう
≫SDGsの目標5の概要や取り組み事例などを解説
SDGs6.安全な水とトイレを世界中に
≫SDGsの目標6の概要や取り組み事例などを解説
SDGs7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
≫SDGsの目標7の概要や取り組み事例などを解説
≫水素関連の最新情報まとめ
≫≫水素ステーションとは?
≫≫水素エネルギーとは?
≫≫水素社会について【前編】
≫≫水素の利用と未来に向けて【後編】
≫≫水素エネルギーの種類
≫石油代替エネルギー
≫アンモニアとは?
≫太陽光パネルのリサイクルと処分
SDGs8.働きがいも経済成長も
≫SDGsの目標8の概要や取り組み事例などを解説
≫離農の原因や対策について解説
SDGs9.産業と技術革新の基盤を作ろう
≫SDGsの目標9の概要や取り組み事例などを解説
≫欧州プラスチック戦略の現状と今後
≫東南アジア諸国の廃プラスチック規制強化
≫環境問題の切り札「生分解性プラスチック」
≫非鉄金属が使用される製品と今後
≫グリーン購入法とは?
≫≫WEEE指令(うぃーしれい)とは?
≫≫RoHS指令(ろーずしれい)とは?
SDGs10.人や国の不平等をなくそう
≫SDGsの目標10の概要や取り組み事例などを解説
SDGs11.住み続けられる街づくりを
≫SDGsの目標11の概要や取り組み事例などを解説
≫持続可能なまちづくりとは?
≫立地適正化計画とは?
≫スマートシティとは?
≫鉄骨造住宅のデメリット(木造住宅との違い)
≫建物の解体と内装工事の違いとは?
≫省エネで補助金とは?
≫ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)
≫米国が定めるクリティカル・ミネラル(重要鉱物)リスト
≫日本の重要鉱物資源リスト
SDGs12.つくる責任、つかう責任
≫SDGsの目標12の概要や取り組み事例などを解説
≫保険該当処分品とは?
SDGs13.気候変動に具体的な対策を
≫SDGsの目標13の概要や取り組み事例などを解説
SDGs14.海の豊かさを守ろう
≫SDGsの目標14の概要や取り組み事例などを解説
≫廃プラ海洋回収船とは?
≫海洋資源鉱物とは?
SDGs15.陸の豊かさも守ろう
≫SDGsの目標15の概要や取り組み事例などを解説
≫鉱物資源政策とは?
SDGs16.平和と公正をすべての人に
≫SDGsの目標16の概要や取り組み事例などを解説
SDGs17.17のパートナーシップで目標を達成しよう
≫リサイクル業者が考える「脱炭素社会に向けて」
有価物ってなに?
スクラップダウンとは?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
≫【産業廃棄物】建設廃棄物を解説
≫【産業廃棄物】一般産業廃棄物を解説
≫【産業廃棄物】特別管理廃棄物を解説
産業廃棄物とは?
≫産業廃棄物の分類と具体的な種類
≫≫【産業廃棄物】あらゆる事業活動に伴う物について
≫≫【産業廃棄物】特定の事業活動に伴う物について
≫廃棄物処理法に関する罰則について
≫【前編】不法投棄とは?過去の不法投棄事件の解説
カーボンニュートラルとは?
バーゼル条約(バーゼル法)とは?
≫【2021年改正】バーゼル法の改正(プラスチック)
≫【2021年改正】バーゼル法の改正(古紙)
≫【2021年改正】バーゼル法の改正(電線・真鍮)
四大公害病とは?高度成長期の日本との関連について
ヨーロッパの太陽光パネル回収システムを解説
脱炭素先行地域とは?【全国26カ所を解説】
東京都の太陽光パネル設置義務化について解説
ゴミの捨て方シリーズ最新版
≫①木材や木製品の正しい処分方法5選!注意点についても解説
≫②石の正しい処分方法5選!やってしまいがちな捨て方についても解説
≫③布団や衣類の捨て方6選!やってはいけない処分方法についても解説
≫④プラスチックは何ゴミになる?量や大きさによって出し方は変わる?
≫⑤家電製品の捨て方は?電池や蛍光灯・LEDはどのように処分すべき?
≫⑥土の正しい処分方法5選!一般ごみとして出せない理由も解説
≫⑦物置の処分方法5選!素材によって捨て方が変わる?
トップページ
LINE
ブログ一覧





















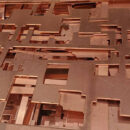
この記事へのコメントはありません。